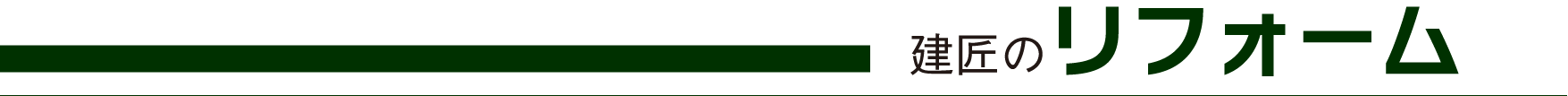
伝統和風住宅の屋根瓦葺き替え

昭和初期の和風住宅
屋根形状は入母屋造り(いりもやづくり)
切妻造りと寄棟造りの二層構造
上部が三角で軒先側へ傾斜しており
下方は四隅へと流れる勾配の屋根となります。
屋根裏は高くて広くなり、通気性が良く夏の暑い日でも屋根からの熱が
伝わり難く暑さの軽減となります。(よく涼しい家とも言われます)
【 屋根瓦の撤去 】
〇当時の瓦の固定は釘留めされていません
野地板(下地板)の上に赤土を瓦形状に敷き
瓦と赤土の粘りだけで接着して葺いています。
屋根形状は入母屋造り(いりもやづくり)
切妻造りと寄棟造りの二層構造
上部が三角で軒先側へ傾斜しており
下方は四隅へと流れる勾配の屋根となります。
屋根裏は高くて広くなり、通気性が良く夏の暑い日でも屋根からの熱が
伝わり難く暑さの軽減となります。(よく涼しい家とも言われます)
【 屋根瓦の撤去 】
〇当時の瓦の固定は釘留めされていません
野地板(下地板)の上に赤土を瓦形状に敷き
瓦と赤土の粘りだけで接着して葺いています。


【 屋根の解体と撤去 】
〇瓦と赤土の撤去後 野地板を剥がし
垂木を丁寧に取り外します。
〇垂木とは棟から軒先まで勾配に傾斜を造る
角材で野地板を平らにする構造材です。
〇野地板が剥がれると屋根の構造材に手を加え
長年の瓦荷重を支えた部材の不具合箇所を調べ
補強や修繕・修理を行います。
〇瓦と赤土の撤去後 野地板を剥がし
垂木を丁寧に取り外します。
〇垂木とは棟から軒先まで勾配に傾斜を造る
角材で野地板を平らにする構造材です。
〇野地板が剥がれると屋根の構造材に手を加え
長年の瓦荷重を支えた部材の不具合箇所を調べ
補強や修繕・修理を行います。

【 破風板の取付 】
〇破風板は” 字のごとく ”
屋根に吹付ける風・雨を遮るための板で
屋根を受ける梁や垂木に風雨が直接当たると
水を吸って、そこから早く腐ってきます。
〇破風板を取ることで屋根を永く守ります。
〇装飾的な意味合いも強く
和風建築での美観的な美しさも際立ちます。
〇破風板の造りは大工の経験と熟練が不可欠で
屋根の大きさ・勾配・長さ・ 建物の立面的外観など
考慮して寸法・形状を決め、装飾的削りなどを行います。
〇檜材で造り檜樹脂の耐水性、防虫性で
腐朽耐候性を高めています。
〇破風板は” 字のごとく ”
屋根に吹付ける風・雨を遮るための板で
屋根を受ける梁や垂木に風雨が直接当たると
水を吸って、そこから早く腐ってきます。
〇破風板を取ることで屋根を永く守ります。
〇装飾的な意味合いも強く
和風建築での美観的な美しさも際立ちます。
〇破風板の造りは大工の経験と熟練が不可欠で
屋根の大きさ・勾配・長さ・ 建物の立面的外観など
考慮して寸法・形状を決め、装飾的削りなどを行います。
〇檜材で造り檜樹脂の耐水性、防虫性で
腐朽耐候性を高めています。

【 上屋根下地 】
〇入母屋造りの上屋根下地が出来上がり
瓦葺きの準備に入ります。
〇入母屋造りの上屋根下地が出来上がり
瓦葺きの準備に入ります。

【 下屋根の解体・撤去 】
〇上屋根の瓦葺きがある程度 出来上がると
下屋根の解体を行います。
〇不具合な部分は修繕・修理して下屋根下地を構成します。
〇上屋根の瓦葺きがある程度 出来上がると
下屋根の解体を行います。
〇不具合な部分は修繕・修理して下屋根下地を構成します。

【 下屋根の左官・板金 】
〇下屋根の瓦葺きも完了し 土壁部分と瓦接合部にステンレス銅メッキ板を取付
壁は漆喰塗りで仕上げます。
〇下屋根の瓦葺きも完了し 土壁部分と瓦接合部にステンレス銅メッキ板を取付
壁は漆喰塗りで仕上げます。

【 最終の仕上げ 】
〇上屋根・下屋根の瓦葺きがほぼ完了
壁の漆喰塗りも完了で雨樋の取付を行っています。
〇上屋根・下屋根の瓦葺きがほぼ完了
壁の漆喰塗りも完了で雨樋の取付を行っています。


【 工事の完成 】
〇兵庫県 淡路島産の『 いぶし瓦 』にて葺替え
〇漆喰塗り壁
〇雨樋の取替え
いぶし瓦は天然粘土を焼いた瓦ですので、四季折々の自然な陽ざしを受ければ
自然な落ち着いた やわらかい風合いで ”いぶし銀” に輝きます。
入母屋造りの伝統的な建築物と『 いぶし瓦 』は最も美しい見栄えと言えるでしょう。
〇兵庫県 淡路島産の『 いぶし瓦 』にて葺替え
〇漆喰塗り壁
〇雨樋の取替え
いぶし瓦は天然粘土を焼いた瓦ですので、四季折々の自然な陽ざしを受ければ
自然な落ち着いた やわらかい風合いで ”いぶし銀” に輝きます。
入母屋造りの伝統的な建築物と『 いぶし瓦 』は最も美しい見栄えと言えるでしょう。



